ドライ加工と金属の切削技術で工具寿命を向上するポイント
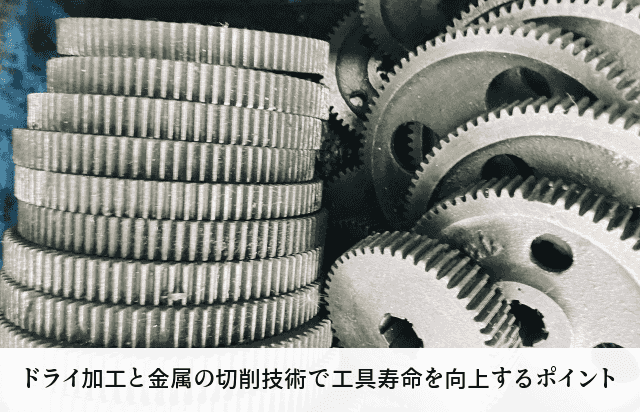
ドライ加工とウェット加工の違いと工具寿命への影響
金属加工の現場では、環境負荷の軽減とコスト削減の観点から、ドライ切削技術への関心が高まっています。ドライ加工とは、金属の切削加工時に切削液を一切使用しない加工方法です。一方、ウェット加工は従来から広く使われている、大量の切削油剤を用いる方法です。
両者の違いを明確にすると、以下のような特徴があります。
- ドライ加工の利点。
- 形成されるチップはクリーンで汚染されておらず、リサイクルが容易
- 切削油剤の送液、ろ過、リサイクル設備が不要で生産システムが簡素化
- 切削油剤や切りくず処理のコストが削減可能
- 環境汚染や安全・品質事故のリスクが低減
- ドライ加工の欠点。
- 直接加工のエネルギー消費が増加し、切削温度が上昇
- 工具とチップの接触部における摩擦状態が変化し、工具摩耗が加速
- 切りくずの制御が難しくなる場合がある
- 加工表面品質が劣化しやすい
工具寿命に関しては、一般的に切削油剤を添加すれば工具寿命が向上すると考えられていますが、実はそうとは限りません。MTUの研究によると、特定の切断速度条件下では、切削油剤の添加プロセスの不連続性と冷却の不均一性により、工具が不規則な冷熱変化を受け、工具先端にクラックが発生して工具寿命を大幅に低下させることがあります。
実際の切削試験では、S45C鋼の旋削加工において、ドライ切削とウェット切削を組み合わせることで、コストとCO2排出量を約40〜43%削減できることが報告されています。これは、適切な条件下でドライ加工を採用することで、工具寿命を損なうことなく環境負荷とコストを削減できる可能性を示しています。
工具コーティング技術による高硬度材料の長寿命化
ドライ加工では工具の熱負荷が高くなるため、適切なコーティング技術の選択が工具寿命を大幅に向上させる鍵となります。近年の切削工具用コーティング技術は飛躍的に進化しており、特にPVD(物理蒸着法)コーティングが注目されています。
PVDコーティングを切削工具に施すことで、以下の特性が向上します。
特に高硬度材料の加工では、最新のコーティング技術が劇的な効果を発揮します。例えば、超硬ボールエンドミルを使用したSKD11(HRC59)の加工において、高硬度・高耐熱被膜のSX-Wに変更することで、従来のTiAlNコーティングと比較して工具寿命が3.5倍以上になった事例が報告されています。
また、微細組織を持つ多層構造のVSX®-MJコーティングは、高温環境における耐酸化性と耐摩耗性、優れた耐クラック性を併せ持ち、高送り加工やドライ加工に最適なパフォーマンスを発揮します。このコーティングを使用した場合、AlCrN系コーティングと比較して約2.5倍以上の寿命を達成したという結果も出ています。
日本国内のコーティング技術は、1985年頃から普及が始まり、単層膜から多層膜、積層膜へと進化してきました。最新のコーティング技術として、TiAlN膜にSiやCrを添加したTiSiN、TiAlSiN、CrAlN膜なども実用化されています。これらの新世代コーティングは、従来よりも高い耐熱性と耐摩耗性を持つため、ドライ加工における工具寿命の延長に大きく貢献します。
日本精密工学会による切削工具のコーティング技術に関する詳細資料
切削条件の最適化で実現する工具寿命の大幅延長
ドライ加工で工具寿命を向上させるためには、切削条件を適切に設定することが極めて重要です。切削速度、送り速度、切り込み深さといった基本パラメータの最適化により、工具にかかる負荷を軽減し、摩耗を最小限に抑えることができます。
工具寿命を延ばすための切削条件最適化のポイントは以下の通りです。
- 切削速度の調整
- 一般に、切削速度が高すぎると工具の摩耗が早まります
- ドライ加工では、適切な工具とコーティングを選定した上で、湿式加工より10〜15%低い切削速度に設定することで、工具寿命が延びる傾向があります
- 高硬度材料の場合、さらに低い切削速度が推奨されます
- 送り速度の最適化
- 送り速度が高すぎると工具に過度な負荷がかかり、摩耗や破損のリスクが高まります
- 送り速度が低すぎると加工時間が長くなり、1点あたりの切削熱が増加します
- 被削材の種類と硬度に合わせた送り速度の選定が重要です
- 切り込み深さの調整
- 切り込みが深すぎると工具に過大な負荷がかかります
- 切り込みが浅すぎると工具が同じ場所を何度も削ることになり、摩擦熱が増加します
- 理想的には、工具の刃先強度と被削材の特性に合わせた切り込み深さを選定します
八戸工業研究所の調査によると、ドライ切削の適用可能性は材料によって大きく異なります。傾きが小さいアルミ系材料や柔らかめの鉄系材料(硬さ95HRB以下)はドライ切削に適していますが、傾きが大きいステンレス系材料やSKD11などの高硬度材料はドライ切削に適さないという結果が出ています。
さらに、寸法精度や表面粗さの要求が低い非閉塞切削加工ではドライ切削を十分に採用できますが、高精度が要求される場合は、主軸回転数の上昇や送り速度の低減などの技術的対策が必要になります。これらの対策によるコスト増加は、切削油剤を使用しないことで節約できるコストとほぼ同等であるため、総合的にはメリットがあると考えられています。
環境負荷を減らしながら工具寿命を向上させるMQL加工
完全なドライ加工と従来の湿式加工の中間に位置するのが、MQL(Minimum Quantity Lubrication)加工です。この方式は「セミドライ加工」とも呼ばれ、極少量の潤滑油をミスト状にして加工点に供給します。従来の湿式加工のように大量の切削油を使う代わりに、1時間あたりわずか4mlから30mlの油剤で加工を行うのが特徴です。
MQL加工の主なメリットは以下の通りです。
- コスト削減効果
- 油剤使用量が圧倒的に少ないため、切削油のコストを大幅に削減
- 廃油処理や清掃作業も軽減され、ランニングコストも抑制
- 工具寿命が延びることで、工具交換頻度を減らし、ダウンタイムを削減
- 環境への配慮
- 環境に優しい生分解性の高い油剤を使用可能
- 工場内の油汚れや滑り事故のリスクも低減
- 廃棄物処理の負担軽減
- 生産性の向上
- 切り屑が乾燥しやすく処理が容易になるため、加工工程の効率化
- 工具寿命の延長による生産性向上
MQL加工の仕組みは、専用のMQL装置を用いて圧縮空気と微量の油剤を混合し、ノズルからミスト状に加工点に吹き付けるというものです。ミストは非常に微細なため、加工点に均一に供給され、優れた潤滑性と適度な冷却効果を発揮します。これにより、工具と被削材の摩擦と摩耗を抑制し、工具寿命の延長、加工精度の向上に貢献します。
環境保護の観点から見ると、MQL加工は特に重要です。切削油剤が関係する環境負荷要因には、塩素系化合物、窒素系化合物、PRTR対象物質などの直接的要因と、大量の油剤供給によるエネルギー消費や廃油発生などの間接的要因があります。MQL加工はこれらの環境負荷を大幅に削減できるため、環境規制が厳しくなる現代の製造業において、非常に有効な選択肢となっています。
ドライ加工時の熱制御戦略:工具寿命向上の新アプローチ
ドライ加工での最大の課題は熱管理です。切削油剤を使用しないことによる冷却効果の欠如は、工具温度の上昇、ひいては工具寿命の短縮につながります。この課題に対して、新たな熱制御アプローチが開発されています。
興味深いのは、CBN(立方晶窒化ホウ素)インサートを使用した加工における知見です。一般的には切削油を使用すると工具寿命が延びると考えられていますが、断続切削の場合は逆効果になることがあります。タンガロイ社の研究によれば、断続切削時に切削油を使用すると、切削中の高温と切削油による急冷のサイクルで「サーマルクラック(熱亀裂)」が発生し、工具寿命が大幅に短くなります。実際の試験では、断続切削時に切削油を使用しない方が、工具寿命が最大4倍も長くなるという驚くべき結果が報告されています。
この知見は、ドライ加工における熱管理の重要性と、必ずしも従来の常識が当てはまらないことを示しています。熱管理の新しいアプローチとして、以下の戦略が注目されています。
- 材料別の熱対策最適化
- 八戸工業研究所の研究によると、材料の硬さと工具寿命予測の傾きには強い相関があります
- 軟らかめの鉄系材料(硬さ95HRB以下)はドライ切削に適しますが、ステンレス系材料などは不向きです
- 材料特性に合わせた熱対策の選択が重要です
- 工具形状と切削経路の最適化
- 熱集中を避ける工具形状の採用
- 切削熱を分散させる切削経路の設計
- 間欠的な切削による冷却時間の確保
- 革新的冷却技術の活用
- 冷風冷却システムの導入
- 中空ドリルロッドを通した空冷システム(MTUの研究では、この方法が切削液使用時よりも良好な結果を示しています)
- 極低温冷却技術(液体窒素など)の応用
- 熱シミュレーションと予測モデルの活用
- 工具寿命予測技術に基づいた最適条件の選定
- 是永らの研究による工具寿命予測式の活用
- デジタルツインによる熱分布のリアルタイム予測と制御
これらの新しい熱制御アプローチを組み合わせることで、ドライ加工環境下でも工具寿命を大幅に延長することが可能になります。特に注目すべきは、必ずしも「ウェット=良い、ドライ=悪い」という単純な図式ではなく、加工条件や材料、工具によって最適な選択が変わるという点です。
工具寿命予測技術と熱制御技術の進化により、ドライ加工はますます実用的になり、環境負荷の低減とコスト削減、そして工具寿命の向上が同時に実現できる時代が到来しています。