面粗度 規格の基礎知識

面粗度 測定方法の種類と特徴
面粗度(表面粗さ)の測定方法は、大きく分けて「接触式」と「非接触式」の2種類があります。それぞれに特徴があり、測定対象や要求精度によって使い分けることが重要です。
接触式測定法

接触式測定は、測定対象物に触針の先端を直接接触させて表面状態を測定する方法です。触針の上下方向の変位を検出することで、表面粗さを数値化します。
【特徴】
- 直接触れるため明確な形状波形が得られる
- 比較的長い距離の測定が可能
- 触針の摩耗や対象物への圧痕が発生する可能性がある
- 評価・解析規格はJIS B 0601(ISO 4287)に準拠
常設タイプ(例:Mitutoyo SURFTEST SJ-410)では、スキッドレス方式を採用しており、触針が直接面粗度の溝に入り込むため、より精密な測定が可能です。ただし、触針が露出しているため取り扱いにはデリケートな注意が必要です。
非接触式測定法
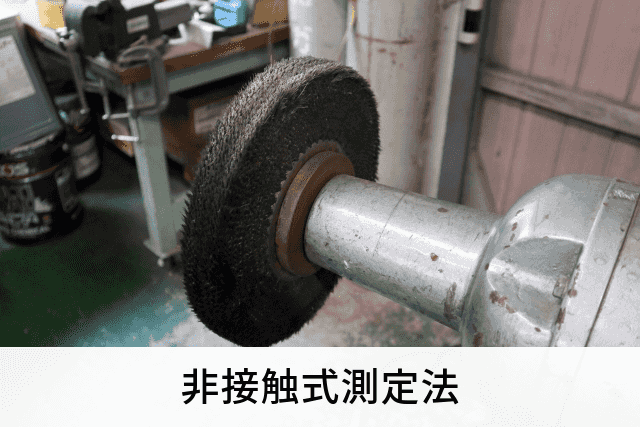
非接触式測定法は、触針の代わりに光やレーザーを用いて表面粗さを計測する方法です。測定原理の違いにより、複数の測定方式があります。
【特徴】
- 触針の摩耗や対象物への圧痕がない
- 測定時間の短縮が可能
- 三次元データ化により多様な解析が可能
- 評価・解析規格はISO 25178に準拠
非接触式測定は、微細な表面や傷つきやすい材料の測定に適しており、近年の測定技術の進化により精度も向上しています。
面粗度 パラメータRaとRzの違いと用途
面粗度を表す代表的なパラメータにはRa、Rz、Ryなどがありますが、それぞれ意味と用途が異なります。適切なパラメータを選択することで、表面品質の管理が効果的に行えます。
Ra(算術平均粗さ)

Raは凸の高さと凹の深さの平均値を表すパラメータです。
【特徴】
- 基準線から上下の面積(凸凹の総面積)を基準長さで割った値
- 数値が小さいほど表面は滑らか
- 突発的に発生した大きな傷の影響は平均化されるため小さい
- 最も一般的に使用されるパラメータ
例えば、Ra0.8は算術平均粗さが0.8μmであることを意味し、一般的な並仕上げレベルに相当します。
Rz(最大高さ粗さ)

Rzは基準長さ内での最大の山頂と最大の谷底の高さの差を表します。JIS B 0601:2001では、かつての「最大高さ」を意味するパラメータとして定義されています。
【特徴】
- 最も高い部分(Rp)と最も深い部分(Rv)の合計値
- 一つでも突出した傷があるとそれが表面粗さの数値になる
- 厳しい表面品質要求に対応するためのパラメータ
ドイツ語の「Zwischen(間)」を語源とし、最高点と最低点の間の高さを表しています。
Rzjis(十点平均粗さ)
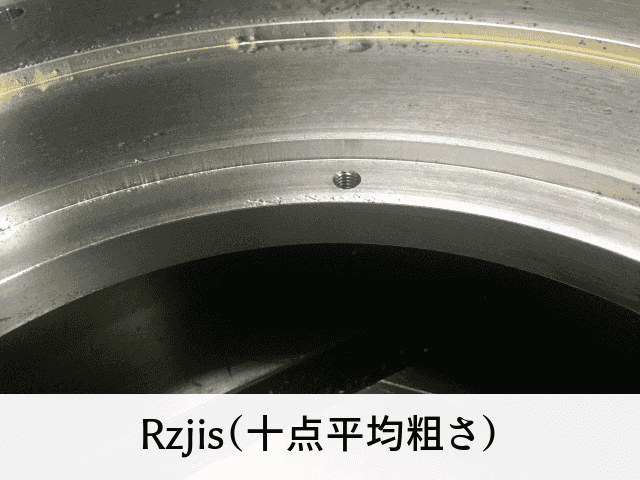
旧JIS規格におけるRzは「十点平均粗さ」を指し、現行の規格ではRzjisとして区別されています。
【特徴】
- 最も高い山頂から5番目までの平均と最も低い谷底から5番目までの平均の和
- 局所的な凹凸の影響を緩和しつつ全体の粗さを評価できる
- 旧規格との互換性が必要な場合に使用
面粗度 JIS規格の変遷と最新動向
面粗さを表すJIS規格は時代とともに進化してきました。測定技術の発展や国際規格との整合性の観点から、複数の改定が行われています。
JIS B 0601:1982(旧規格)
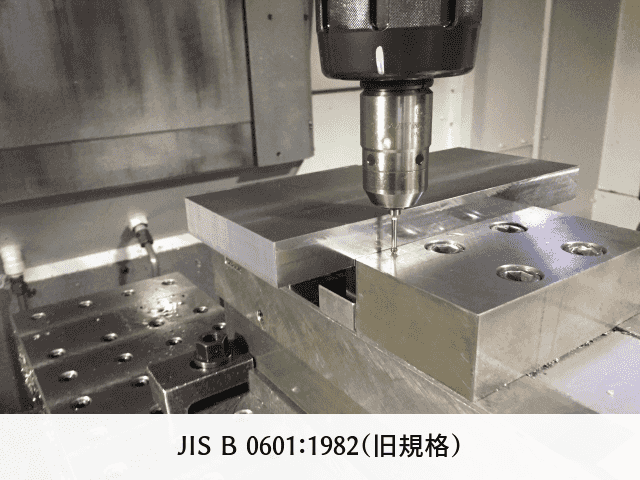
最初の近代的な表面粗さ規格で、以下の特徴がありました。
- 「中心線平均粗さ」としてRaを定義
- 「最大高さ」をRmaxとして定義
- 「十点平均粗さ」をRzとして定義
- 2CR特性のフィルタで減衰率75%になる波長をカットオフ値とする
JIS B 0601:1994(中間改定)
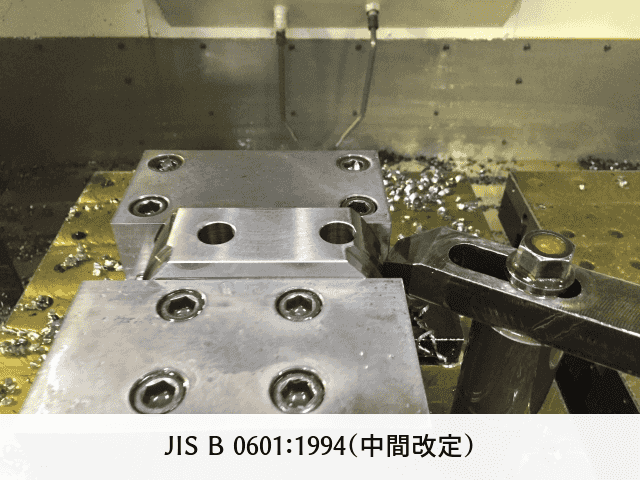
国際的な整合性を高めるための改定が行われました。
- 「算術平均粗さ」としてRaの名称を変更
- 「最大高さ」をRyとして定義
- 減衰率が50%になる波長をカットオフ値とする位相補償型フィルタを採用
JIS B 0601:2001(現行規格)
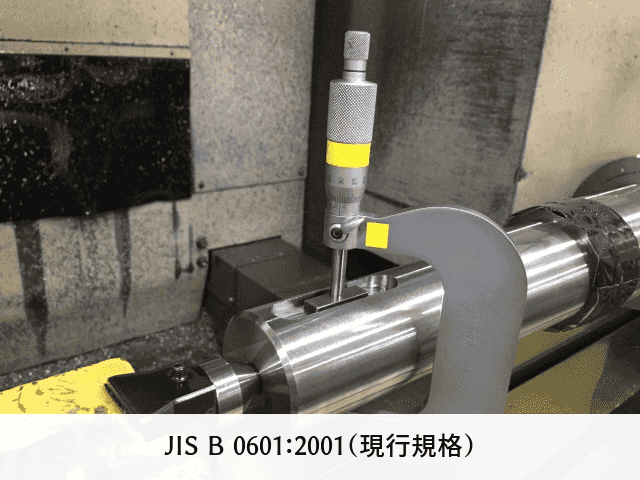
ISO 4287:1997に準拠した現在の規格です。
- パラメータの大幅な増加と定義の変更
- 「最大高さ」をRzとして再定義(旧Rzは十点平均粗さから最大高さに変更)
- 「十点平均粗さ」はRzJISとして付属書に記載
- 短波長成分を遮断するカットオフ値λsの定義
- 指示値と測定値を比較するための新ルール(16%ルール & 最大値ルール)の導入
この変更により、Rzの意味が「十点平均粗さ」から「最大高さ」に変わった点は特に重要で、図面解釈時に注意が必要です。
ISO 25178の導入
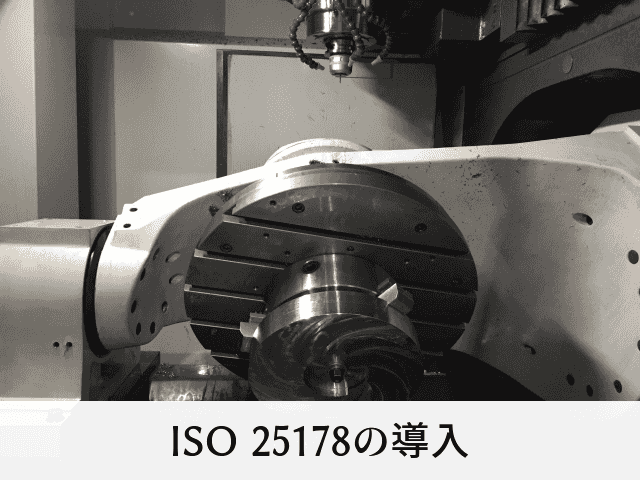
三次元測定に対応した新たな国際規格として、ISO 25178が導入されています。この規格では。
- 面性状(面粗さ測定)の三次元評価が可能
- 山頂点、谷底点、鞍点などの三次元特性を定義
- 非接触式測定に適した評価基準を提供
面粗度 標準値と金属加工における活用法
金属加工において、面粗度は製品の品質や機能性に直接影響します。各加工方法に応じた適切な面粗度を理解し、活用することが重要です。
加工方法と達成可能な面粗度
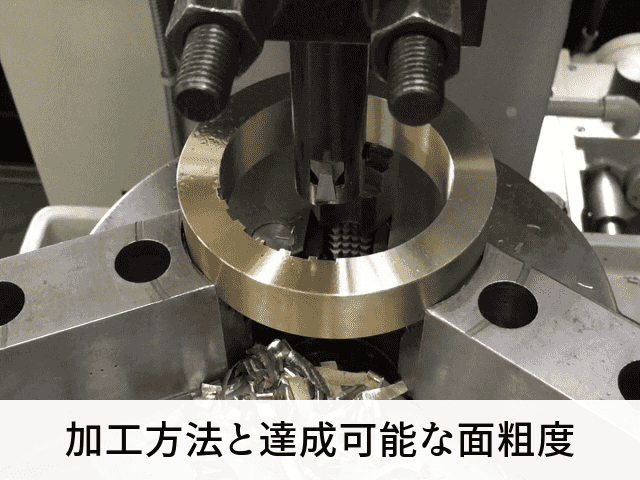
一般的な金属加工方法と達成可能な面粗度の目安です。
| 加工方法 | 達成可能なRa値(μm) | 一般的な用途 |
|---|---|---|
| 鋳造 | 12.5~25 | 構造部品 |
| 旋削(荒加工) | 6.3~12.5 | 一般機械部品 |
| 旋削(仕上げ) | 1.6~3.2 | 機械摺動部 |
| フライス加工 | 3.2~6.3 | 一般機械部品 |
| 研削 | 0.8~1.6 | 精密部品 |
| ラップ加工 | 0.1~0.4 | 精密嵌合部 |
| 鏡面研磨 | 0.025~0.1 | 光学部品、金型 |
面粗度記号の実践的な読み方
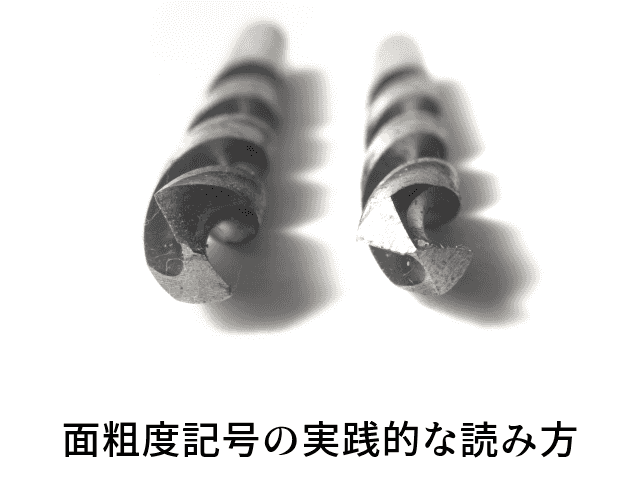
図面に表示される面粗度記号の基本的な読み方です。
- 三角記号(▽、▽▽、▽▽▽):旧JIS規格による表示
- 数値表記(Ra0.8、Rz3.2など):現行規格による表示
旧規格と新規格の対応関係の目安。
- ▽:Ra25、Ry100、Rz100相当
- ▽▽:Ra3.2、Ry12.5、Rz12.5相当
- ▽▽▽:Ra1.6、Ry6.3、Rz6.3相当
金属加工における面粗度の重要性
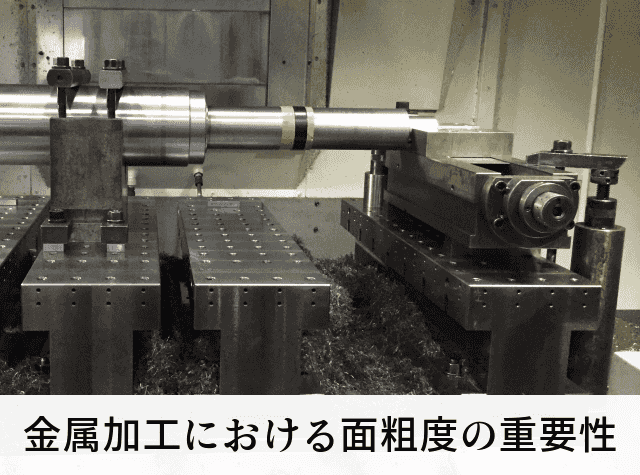
面粗度は以下の製品特性に影響します。
- 摩擦特性:摺動部品の面粗度は摩擦係数に直接影響し、動作性能や寿命を左右します
- 密着性:接合部の面粗度は密着性や気密性に影響します
- 外観品質:装飾部品では面粗度が光の反射特性に影響し、美観を決定します
- 耐食性:表面の凹凸は腐食の起点になるため、耐食性要求の高い部品では低い面粗度が求められます
加工コストと面粗度は密接に関連しており、必要以上に低い面粗度を指定すると、工程数の増加によりコストが上昇します。例えば、Ra0.8から0.4への向上には追加工程が必要になることが一般的です。
面粗度 測定時の誤差要因と対策テクニック
面粗度測定において高い精度を確保するためには、様々な誤差要因を理解し、適切な対策を講じる必要があります。
主な誤差要因
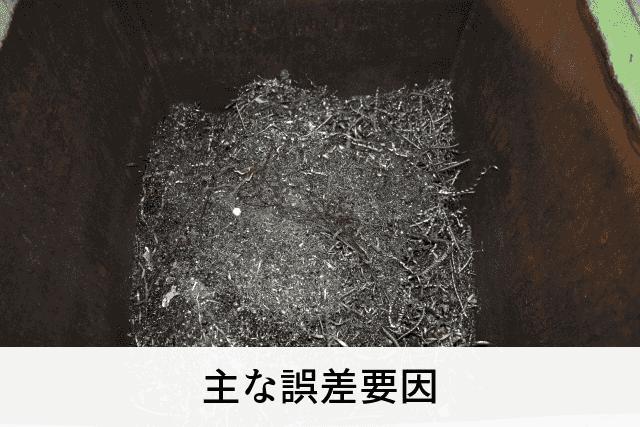
- 測定機器の違いによる誤差
測定機の構造や原理の違いにより、同じ部品を測定しても異なる結果が出ることがあります。例えば、常設タイプ(Mitutoyo SURFTEST SJ-410)とハンディタイプ(SJ-210)では、以下のような測定値の差異が報告されています。
| 測定面 | 常設タイプ | ハンディタイプ | 差異 |
|---|---|---|---|
| サンプル1 | Ra0.354μm | Ra0.338μm | 0.016μm |
| サンプル2 | Ra0.180μm | Ra0.165μm | 0.015μm |
| サンプル3 | Ra0.064μm | Ra0.033μm | 0.031μm |
- 触針構造による誤差
ハンディタイプの測定器は「スキッド」と呼ばれるパーツが触針を覆い、測定面に接触します。このスキッドが基準となるため、スキッドレスの常設タイプとは測定値に差が生じます。特に精密な測定が求められる場合はスキッドレスタイプの使用が推奨されます。
- 測定条件による誤差
カットオフ値(λc)や評価長さの設定によっても測定結果は変化します。JIS規格では測定条件の標準化が進められていますが、条件の違いに注意が必要です。
精度向上のテクニック
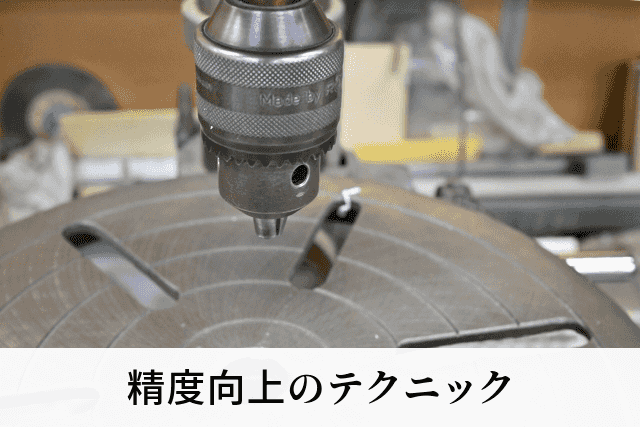
- 適切な測定機器の選択
測定対象の特性に合わせた測定機器の選択が重要です。
- 高精度測定が必要:常設タイプ(スキッドレス)
- 現場での測定:ハンディタイプ
- 三次元形状評価:非接触式
- 測定環境の整備
以下の環境要因が測定精度に影響します。
- 振動:測定中の振動は誤差の原因になるため、防振対策が必要
- 温度:温度変化による測定物や測定機の熱膨張が誤差を生じる
- 清浄度:微細なゴミや油膜が測定結果に影響する
- 適切な測定パラメータの設定
規格に基づいた適切なパラメータ設定が重要です。
- カットオフ値(λc):表面特性に応じた適切な値を選択
- 触針先端半径:小さな半径ほど微細な凹凸を検出できるが、摩耗しやすい
- 測定力:小さな測定力ほど測定物への影響が少ないが、追従性が低下
- 多点測定と統計処理
単一測定ではなく、複数箇所の測定と統計処理により信頼性の高い評価が可能になります。JIS規格では16%ルールと最大値ルールという新しい統計的評価方法が導入されています。
KEYENCEの面粗さ用語解説 - ISO 25178に基づく三次元測定の詳細情報
ミツトヨの表面粗さJIS規格解説 - 規格変更の詳細と測定方法について
金属加工業界では、面粗度の適切な理解と管理が製品品質の向上と生産コストの最適化に不可欠です。JIS規格の変遷を理解し、目的に応じた測定方法とパラメータを選択することで、より効果的な品質管理が実現できます。また、測定時の誤差要因を把握し、適切な対策を講じることで、信頼性の高い測定結果を得ることができます。
表面粗さの専門知識は、金属加工技術者のスキルの一つとして、ますます重要性を増しています。最新の規格動向にも注目しながら、実務に活かしていくことが大切です。